ここが知りたい質疑 議案審議
(当初予算、補正予算)
当初予算
町民課
「書かない窓口」
新たな動きは
新たな動きは
問 コロナ禍で「書かない窓口」が浸透したが、次年度に向け新しい動きはあるか。
答 現在は窓口に来ずとも役場本庁舎、コンビニで自動交付機により戸籍情報等取得できる。
昨年比1.5倍の利用率であり、今後も利用を伸ばしたい。

役場本庁にある戸籍等の自動交付機
答 現在は窓口に来ずとも役場本庁舎、コンビニで自動交付機により戸籍情報等取得できる。
昨年比1.5倍の利用率であり、今後も利用を伸ばしたい。

標準化作業と重複しないか
問 次年度の戸籍・住基システムを改修することは、3年後の地方公共団体の基幹業務システムの標準化作業と重複しないか。
答 システム構築については具体的な内容は未だない。国の様子を見ながら検討する。
答 システム構築については具体的な内容は未だない。国の様子を見ながら検討する。
本人確認は一度で済むか
問 本庁舎はワンストップ窓口だが、複数の課に申請する場合には本人確認書類の記入は一度で済むのか。
答 各課により様式が違うため負担をかけているが、同じ内容を何度も書くことが無いように努めていきたい。
答 各課により様式が違うため負担をかけているが、同じ内容を何度も書くことが無いように努めていきたい。
新婚世帯支援住宅になぜ変更
問 日義地区の子育て支援住宅の建設地を、新婚世帯支援住宅に変更した理由は。
答 移住定住促進の側面からも、先ずは若者世代に住宅を提供し育てできるような環境につなげたい思いである。
答 移住定住促進の側面からも、先ずは若者世代に住宅を提供し育てできるような環境につなげたい思いである。
子育て支援住宅の状況は
問 子育て支援住宅は、日義地区、三岳地区にあるが状況は。
答 両地区とも入居率は高く、十分活用されている。

子育て支援住宅
答 両地区とも入居率は高く、十分活用されている。

所得金額制限を緩和できないか
問 子育て支援住宅の入居には所得制限があり、結婚新生活支援事業の補助金にも夫婦2人の所得制限がある。人口流出を防ぐためにも所得金額制限の緩和はできないか。
答 町の公営住宅で需要が高いものについて研究をしていきたい。
答 結婚新生活支援事業については、来年度から年齢・所得が緩和され、補助金額は増額になり事業は拡大されている。(企画財政課)
答 町の公営住宅で需要が高いものについて研究をしていきたい。
答 結婚新生活支援事業については、来年度から年齢・所得が緩和され、補助金額は増額になり事業は拡大されている。(企画財政課)
保健福祉課
補正具など購入助成の内容は
問 がん患者の外的変更を補完する補正具など、購入費用助成の具体的内容は。
答 がん患者の社会参加を支援するため、医療用ウィッグや乳房補正具を購入する場合に、その一部を補助する。
答 がん患者の社会参加を支援するため、医療用ウィッグや乳房補正具を購入する場合に、その一部を補助する。
帯状疱疹 ワクチンの補助できないか
問 日本で60万人が毎年かかる、決して珍しくない帯状疱疹。ワクチンで防げるが費用が4万4000円と高額。補助できないか。
答 6000円ほどの水痘ワクチンでも予防できる。
答 6000円ほどの水痘ワクチンでも予防できる。
子宮頸 がんワクチンの取り組みは
問 次年度の子宮頸がんワクチン予防接種の取り組みは。
答 国からは定期接種に入ると通知があり、町としても要綱の改正を予定している。実施できなかった期間があったので対象者には通知をしているが接種率が上がっていない。今後も広報等でPRしていく。
答 国からは定期接種に入ると通知があり、町としても要綱の改正を予定している。実施できなかった期間があったので対象者には通知をしているが接種率が上がっていない。今後も広報等でPRしていく。
建設農林課
まきストーブ補助 少ないのでは
問 木質バイオマス推進事業の中で、まきストーブ購入の補助金が少ないのでは。
答 需要の声を聴きながら検討していきたい。

補助率アップが求められているまきストーブ
答 需要の声を聴きながら検討していきたい。

世界を対象に農産品の検討を
問 日本の農産品輸出額が1兆円を超えている。木曽町の特徴ある農産品を世界対象に検討できないか。
答 木曽の農業が非常に厳しい状況であることは認識している。新たな市場を見い出すのは必要。世界展開まではいかなくとも、スモール農業の中でどう展開していくか検討している。
答 木曽の農業が非常に厳しい状況であることは認識している。新たな市場を見い出すのは必要。世界展開まではいかなくとも、スモール農業の中でどう展開していくか検討している。
原木乾燥の場所や規模は
問 木質バイオマス事業で、チップを原木のまま乾燥させるとのこと。場所と規模は。
答 黒川の橋詰地区を考えている。広さは約4500㎡で、舗装面積は2500㎡程度。残りは搬出材の仕分けや集成材工場などの利用を検討する。現在の場所は乾燥原木をチップ化する場所として利用する。
問 工事の残土処理はどのような考えか。
答 発生土処分地が不足している。工事の都度工夫をして検討する。大原のグラウンドなども一時的には活用したい。
問 大原のグラウンドまでの道は生活道路にもなっており、日義と大原を結ぶ橋は狭い。大型のトラックが通る場合のことも考えた対応も検討してほしい。
答 大原への橋が狭いことは認識している。地域協議会からの要望もあり、橋の架け替えの必要性も認識しているが、優先性なども踏まえて検討していく。
答 黒川の橋詰地区を考えている。広さは約4500㎡で、舗装面積は2500㎡程度。残りは搬出材の仕分けや集成材工場などの利用を検討する。現在の場所は乾燥原木をチップ化する場所として利用する。
問 工事の残土処理はどのような考えか。
答 発生土処分地が不足している。工事の都度工夫をして検討する。大原のグラウンドなども一時的には活用したい。
問 大原のグラウンドまでの道は生活道路にもなっており、日義と大原を結ぶ橋は狭い。大型のトラックが通る場合のことも考えた対応も検討してほしい。
答 大原への橋が狭いことは認識している。地域協議会からの要望もあり、橋の架け替えの必要性も認識しているが、優先性なども踏まえて検討していく。
森林経営管理推進事業とは
問 森林経営管理推進事業の中で、森林計画策定計画委託と現況調査委託はどのような内容か。
答 具体的な森林計画アクションプラン策定とその前段として民有林の林相判読調査を委託する。

カラマツ材などが伐り出される現場
答 具体的な森林計画アクションプラン策定とその前段として民有林の林相判読調査を委託する。

アクションプランは自ら策定を
問 アクションプランを策定する場合は委託ではなく、町自ら策定すべき。
答 全て委託で実施するのではなく町で策定していく。林相判読調査結果を踏まえアクションプランのたたき台を委託するもの。
答 全て委託で実施するのではなく町で策定していく。林相判読調査結果を踏まえアクションプランのたたき台を委託するもの。
広域連合との連携は
問 森林経営管理制度は広域連合でも実施している。どのように連携していくのか。
答 日義や開田、三岳などの保育間伐整備地域を候補に挙げ、広域連合の森林整備推進室と連携して実施していく。
答 日義や開田、三岳などの保育間伐整備地域を候補に挙げ、広域連合の森林整備推進室と連携して実施していく。
観光商工課
スキー場の運営状況は
問 木曽福島スキー場とマイアスキー場の運営状況は。
答 3月12日現在の入り込みは、木曽福島スキー場は昨年度と比較して108%、マイアスキー場は49%となっている。
電気代などの支出経費が大幅増となり経営を圧迫しているが、飲食の提供などに工夫を凝らし集客を図っている。

スキーヤーでにぎわう木曽福島スキー場
答 3月12日現在の入り込みは、木曽福島スキー場は昨年度と比較して108%、マイアスキー場は49%となっている。
電気代などの支出経費が大幅増となり経営を圧迫しているが、飲食の提供などに工夫を凝らし集客を図っている。

スキー場負担金による整備費のチェックは
問 マイアスキー場の負担金1億2千万円が計上されているが、施設整備費のチェックはどのように実施するのか。
答 今年度支出した負担金については、使途の内容を報告するよう連絡している。領収書の提示も求め内容をチェックする。来年度も同様の考えである。
答 今年度支出した負担金については、使途の内容を報告するよう連絡している。領収書の提示も求め内容をチェックする。来年度も同様の考えである。
ワークセンターの効果はあるか
問 ワークセンター(ふらっと木曽)は建設から5年が経過した。売り上げ及び収益はどうなっているか。
答 今年度の収入見込みは135万4000円でコロナ前の令和2年度と比較して166%の増となっている。コロナ禍の中でコワーキングやリモートワークが一般的になってきており、運営は評価されている。

運営が評価されているワークセンター(ふらっと木曽)
答 今年度の収入見込みは135万4000円でコロナ前の令和2年度と比較して166%の増となっている。コロナ禍の中でコワーキングやリモートワークが一般的になってきており、運営は評価されている。

ロープウェイの管理費用提示は
問 御岳ロープウェイの運営について、指定管理者方式として実施するとのこと。その費用はいつ提示するのか。
答 例年実施の索道整備費用1億円、指定管理費3500万円は未だ予算化はしていない。スキー場等あり方検討委員会で協議して4月には提示する予定。修理費などは現在、見積もりを取っている。従来通り索道の整備費用と運営の指定管理費に分けて予算化を考えている。
答 例年実施の索道整備費用1億円、指定管理費3500万円は未だ予算化はしていない。スキー場等あり方検討委員会で協議して4月には提示する予定。修理費などは現在、見積もりを取っている。従来通り索道の整備費用と運営の指定管理費に分けて予算化を考えている。
議員や職員の施設利用を
問 スキー場などの施設に議員や職員の利用が望まれるが、職員に対する働きかけはどうなっているか。
答 職員互助会を通じて利用を呼びかけている。また、職員にとどまらず町民への呼びかけも積極的に行っている。
答 職員互助会を通じて利用を呼びかけている。また、職員にとどまらず町民への呼びかけも積極的に行っている。
市街地活性化の核に位置付けては
問 来年度は中心市街地の人口分析調査を実施する。ワークセンターを中心市街地の核になるように位置付けては。
答 ほかの施設やまちづくり木曽福島などの団体もあるので、連携して交流人口の拠点となるようにしたい。
答 ほかの施設やまちづくり木曽福島などの団体もあるので、連携して交流人口の拠点となるようにしたい。
教育委員会
木曽音楽祭の将来は
問 木曽音楽祭の将来についてどう考えているか。
答 現在過渡期にあると感じている。さまざまな課題を明確にして解決し、続けていきたい。

3年ぶりに開催の木曽音楽祭
答 現在過渡期にあると感じている。さまざまな課題を明確にして解決し、続けていきたい。

中学校体育館にエアコン設置を
問 木曽町中学校体育館にエアコンを設置できないか。
答 まだ教室に設置されていない学校があり、順番に設置していく。
答 まだ教室に設置されていない学校があり、順番に設置していく。
郷土館をどう考えるか
問 木曽福島郷土館についてどう考えているか。
答 老朽化しており新しいものを造りたい。八十二銀行跡地の利用も含めて検討したい。
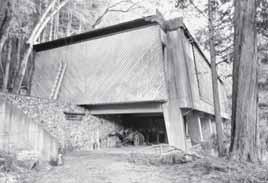
老朽化が著しい木曽福島郷土館
答 老朽化しており新しいものを造りたい。八十二銀行跡地の利用も含めて検討したい。
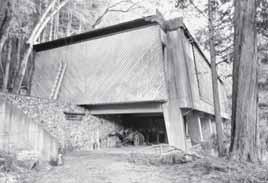
ジュニアスポーツクラブ構想とは
問 ジュニアスポーツクラブ構想について詳しい説明を。
答 令和5年4月より地域スポーツカルチャーを立ち上げ、子どもたちがいつでも好きな文化活動、スポーツ活動ができる環境を地域ぐるみで創り上げていくというもの。学校も関わっており、先生にも参加してもらうことになっている。現在、ヒアリングは終了、課題の整理を行っている。
答 令和5年4月より地域スポーツカルチャーを立ち上げ、子どもたちがいつでも好きな文化活動、スポーツ活動ができる環境を地域ぐるみで創り上げていくというもの。学校も関わっており、先生にも参加してもらうことになっている。現在、ヒアリングは終了、課題の整理を行っている。
教材費など公費負担で事務処理は
問 教材費や修学旅行費が全額公費負担することで、今まで学校で行っていた事務処理はどうなるか。
答 保護者の負担が減り、先生の事務処理もなくなるので働き方改革にもなる。
答 保護者の負担が減り、先生の事務処理もなくなるので働き方改革にもなる。
日義支所
巴庵の利活用は
問 義仲館に隣接する巴庵の利活用や義仲館と他の観光資源との組み合わせをどう考えているか。
答 周辺の観光資源を使いサイクルツーリズムや義仲ウォーキングなどを推進していく。巴庵も復活させていく。

建物の利活用が望まれる巴庵
答 周辺の観光資源を使いサイクルツーリズムや義仲ウォーキングなどを推進していく。巴庵も復活させていく。

開田支所
やまゆり荘の食堂再開は
問 やまゆり荘について、休業している食堂営業を再開するつもりはないか。
答 今のところ直営では無理で、今後については検討中。指定管理も含め再開の道を探る。
答 今のところ直営では無理で、今後については検討中。指定管理も含め再開の道を探る。
トラクター管理は十分か
問 トラクターの更新事業について、管理はどこで行っているのか。また、管理は十分にできているのか。
答 振興公社できちんと管理している。
答 振興公社できちんと管理している。
補正予算
一般会計補正予算
93%の繰越明許費
体制づくり必要では
体制づくり必要では
問 農業施設等の災害復旧工事に係る繰越明許費は、当初予算の93%ほどになっている。応札がない、同じ会社が複数随意契約し工事が進まないなどの理由があると思われるが、年度内に終わるよう体制づくりが必要では。
答 設計金額に応じて入札の種類を決めている。一般競争入札で応札がなく不調になった場合については再度入札に付す。それでも不調に終わった場合は、選定委員会で指名競争入札に切り替える。または、事業者と相談して随意契約にするなど対応に努めている。

農業用水路復旧工事
答 設計金額に応じて入札の種類を決めている。一般競争入札で応札がなく不調になった場合については再度入札に付す。それでも不調に終わった場合は、選定委員会で指名競争入札に切り替える。または、事業者と相談して随意契約にするなど対応に努めている。

繰越明許から事業進めるよう協議を
問 災害復旧工事で繰越明許となった案件から事業を進めるように、事業者と協議してほしい。
答 来年度は事業者の手も空いてくる予定。できるだけ繰越明許となっている事業から着手していただくように要望している。
答 来年度は事業者の手も空いてくる予定。できるだけ繰越明許となっている事業から着手していただくように要望している。