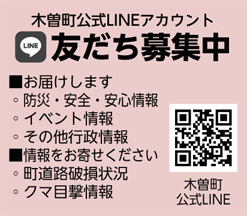ここが知りたい質疑 議案審議
決算認定
総務課
正規職員増やす考えは
問 役場の正規職員より会計年度任用職員の方が多いが、正規職員を増やす考えは。
答 こども園、学校など任用職員に頼らざるを得ない状況である。令和4年度は退職者が多く、新規採用の応募が少なかった要因もあったが、来年度は正規職員を増やしたい。
答 こども園、学校など任用職員に頼らざるを得ない状況である。令和4年度は退職者が多く、新規採用の応募が少なかった要因もあったが、来年度は正規職員を増やしたい。
会計年度職員の手当等は適切か
問 会計年度任用職員制度が始まり3年。期末手当や昇給など適切に行われているか。
答 昇給・期末手当の支給をしている。来年度から勤勉手当の支給も可能になる。また、旧嘱託職員を中心に勤勉手当の支給についても検討したい。待遇の改善について常に見直していく。
答 昇給・期末手当の支給をしている。来年度から勤勉手当の支給も可能になる。また、旧嘱託職員を中心に勤勉手当の支給についても検討したい。待遇の改善について常に見直していく。
投票率の状況は
問 近年、投票率の低下が問題になっている。町の投票率の状況は。
答 令和4年県知事選挙では、投票率が高い70代が76%、10代は40%、20代44%である。
答 令和4年県知事選挙では、投票率が高い70代が76%、10代は40%、20代44%である。
投票促す取り組み必要では
問 若い世代に投票行動を促す取り組みが必要では。
答 選挙管理委員会、県と共に主権者教育も含め活動している。学校等でも選挙について身近な問題として取り組んでいきたい。
答 選挙管理委員会、県と共に主権者教育も含め活動している。学校等でも選挙について身近な問題として取り組んでいきたい。
電子申請で何ができるか
問 マイナンバーカードの行政手続きオンライン化では、電子申請で何ができるのか。
答 子育て関係で15の手続き、介護関係では11の手続きが申請可能。具体的には児童手当等受給資格及び児童手当の認定請求、保育施設等利用申し込み、要介護・要支援認定申請などが電子申請でできる。
答 子育て関係で15の手続き、介護関係では11の手続きが申請可能。具体的には児童手当等受給資格及び児童手当の認定請求、保育施設等利用申し込み、要介護・要支援認定申請などが電子申請でできる。
ペーパーレス化の評価は
問 庁内でペーパーレス化を推進しているが、その評価は。
答 年間50回ほどタブレットを使った会議を行い、ペーパーレスにより環境負荷の低減につながった。
答 年間50回ほどタブレットを使った会議を行い、ペーパーレスにより環境負荷の低減につながった。
企画財政課
地域資源研究所の成果は
問 地域資源研究所事業での結果と成果は。
答 見えづらい事業であるが、令和5年は乳酸菌を売り出すために菌に名前を付ける。問い合わせがある企業と連携して売り出していきたい。
問 地域資源研究所はスンキの乳酸菌だけでなく、新商品や派生商品の開発にも取り組んで欲しいが。
答 今までは研究が主で成果を出すことは余りなかった。今後は地元企業や町の加工連などと連携し売り出していきたい。
答 見えづらい事業であるが、令和5年は乳酸菌を売り出すために菌に名前を付ける。問い合わせがある企業と連携して売り出していきたい。
問 地域資源研究所はスンキの乳酸菌だけでなく、新商品や派生商品の開発にも取り組んで欲しいが。
答 今までは研究が主で成果を出すことは余りなかった。今後は地元企業や町の加工連などと連携し売り出していきたい。
統一した発酵食品はないか
問 発酵のまち・木曽町である。飲食店や旅館で統一した発酵食品やアピールする物はないのか。
答 未だ売り出す商品が少ない。ダム施設内で貯蔵熟成した酒・味噌・チーズなどうまみ成分の研究を進め旅館などで提供できるよう勧めたい。
答 未だ売り出す商品が少ない。ダム施設内で貯蔵熟成した酒・味噌・チーズなどうまみ成分の研究を進め旅館などで提供できるよう勧めたい。
大府市との協定の役割は
問 木育の推進等で大府市、王滝村と連携協定を結んだ。その役割と使命は。
答 王滝村の木材を使い木曽町で木工や木育、木工製品などの活用を進める。おもちゃ美術館を中心に当町を利用していただきたい。

左から越原王滝村長、岡村大府市長、原木曽町長
答 王滝村の木材を使い木曽町で木工や木育、木工製品などの活用を進める。おもちゃ美術館を中心に当町を利用していただきたい。

おもちゃ美術館料金 安くならないか
問 おもちゃ美術館の料金設定は、もう少し安くはならないか。
答 生涯学習課と子育て教育課の予算で小学生以下は無料、教員等も学校行事では公費で支出している。独立採算の施設であり現行の料金の軽減は考えていない。
答 生涯学習課と子育て教育課の予算で小学生以下は無料、教員等も学校行事では公費で支出している。独立採算の施設であり現行の料金の軽減は考えていない。
人口分析調査の具体的取り組みは
問 人口分析調査事業を各地域で行っているが、具体的な取り組みは。
答 各地域での取り組みはなかなか進んでいないが、日義地域協議会では移住プロジェクトを進めている。主に問題提起になってしまっているため、もっと踏み込んだ内容にしたい。
答 各地域での取り組みはなかなか進んでいないが、日義地域協議会では移住プロジェクトを進めている。主に問題提起になってしまっているため、もっと踏み込んだ内容にしたい。
広域連携事業の結婚支援とは
問 若者交流事業の負担金で、広域連携事業結婚支援とは。
答 幹事町村でチラシを作り、主にマッチングイベントを行っている。38名が参加し9組のカップルが成立している。
答 幹事町村でチラシを作り、主にマッチングイベントを行っている。38名が参加し9組のカップルが成立している。
町単独でも結婚など意識啓発をすべきでは
問 広域連合だけでなく町単独でも結婚・出産に対する意識啓発を行うべきでは。
答 現状では子どもが生まれてからの補助制度が手厚い。難しい課題だが検討したい。
答 現状では子どもが生まれてからの補助制度が手厚い。難しい課題だが検討したい。
保健福祉課
精神科以外の負担率 一律にできないか
問 精神障害を持っている方が精神科以外を受診した際の負担率を、精神科負担率と一律にできないか。
答 指定医療機関・指定薬局に関しては、1割負担。それ以外は普通の健康保険があるため3割負担の適用となる。福祉医療の受給者の対象であれば、その後福祉医療費でその分返還される。
答 指定医療機関・指定薬局に関しては、1割負担。それ以外は普通の健康保険があるため3割負担の適用となる。福祉医療の受給者の対象であれば、その後福祉医療費でその分返還される。
老人施設に認知症の方が措置入所しているが
問 養護老人福祉施設に、認知症がかなり進行した方が措置入所している現状があるが。
答 木曽広域連合に入所を申請後、認知症が進行した場合は、状況により介護申請を経て特別養護老人ホーム等の介護施設へ変更される。ケースによるので相談して欲しい。
答 木曽広域連合に入所を申請後、認知症が進行した場合は、状況により介護申請を経て特別養護老人ホーム等の介護施設へ変更される。ケースによるので相談して欲しい。
シニアがスマホを学ぶ機会を
問 デジタル化が進み、シニアクラブでもスマートフォンに慣れるために勉強したいという声が挙がっている。町としてさまざまな形で機会を設けて欲しい。
答 人数が集まれば事業者が出向くサービスもあるので、事務局に相談して欲しい。

シニアにも広まっているスマホ
答 人数が集まれば事業者が出向くサービスもあるので、事務局に相談して欲しい。

コロナワクチン 経過後の効果検証を
問 新型コロナワクチンの効果は時間経過に伴って減っていく。効果について検査・検証して欲しい。
答 現在の段階では考えていない。
答 現在の段階では考えていない。
町民課
マイナンバーカード 説明十分か
問 1名がマイナンバーカードを返納した。作成および返納の申請時にメリット・デメリットの説明は十分にしているか。
答 作成は任意であるので誤解のないように説明している。返納した人には1000円で再発行できる案内もした。
答 作成は任意であるので誤解のないように説明している。返納した人には1000円で再発行できる案内もした。
空き家解消の見通しは
問 空き家対策は専任者を配置して活用も増えてきた。人員不足が心配されるが空き家解消に向けて進んでいけるか。今後の見通しは。
答 他の業務との兼任で2名配置し移住サポートセンターの協力も得ている。業務量は増えてきたが現行の体制で進めていく。移住定住対策、空き家対策は非常に重要な課題であり、しっかり推進していかなければならない。全体の業務量やバランスを考慮しながら、必要であれば増員を含めて検討していきたい。
答 他の業務との兼任で2名配置し移住サポートセンターの協力も得ている。業務量は増えてきたが現行の体制で進めていく。移住定住対策、空き家対策は非常に重要な課題であり、しっかり推進していかなければならない。全体の業務量やバランスを考慮しながら、必要であれば増員を含めて検討していきたい。
移住者の生計は成り立っているか
問 移住して来た方々の生計は成り立っているか。また、移住の理由をまとめる等しているか。
答 芸術的な分野やリモートワーク、また起業する方がいる一方、町内の製造業、建設業に就職した人もいる。木工関係を選択する方が多いことが一つの特徴として挙げられる。
答 芸術的な分野やリモートワーク、また起業する方がいる一方、町内の製造業、建設業に就職した人もいる。木工関係を選択する方が多いことが一つの特徴として挙げられる。
木曽町診療所
診療所にジェネラリストを
問 医師不足が深刻な状況が続いているが、診療科目を絞らない医師「ジェネラリスト」の育成に取り組む大学が増えている。診療所にジェネラリストを手配できるよう模索してはどうか。
答 県や県内の連合会、信州大学等に相談しているところである。機会を捉えながら検討したい。
答 県や県内の連合会、信州大学等に相談しているところである。機会を捉えながら検討したい。
国民健康保険
特定健診の受診率向上を
問 特定健診が平日、昼間だと受診できない人がいる。聞き取り等、特定健診の受診率向上のために取り組みを。
答 現在も休日に1日受診できる。声掛けしたり、未受診者にアンケートを実施したり等良い方向を見出していきたい。
答 現在も休日に1日受診できる。声掛けしたり、未受診者にアンケートを実施したり等良い方向を見出していきたい。
オンライン診療に向け努力を
問 オンライン診療が今後の医療の大きな流れの一つになる。この体制に近づけていく努力を。
答 木曽病院と上松の1地区をモデルとして往診を併用したオンライン診療が始まったが定期的な診察、病状が一定の皆さんが対象であり、現在はさまざまに対応できるものではない。広域的に検討も含め少しずつ様子を見ながら拡大していきたい。
答 木曽病院と上松の1地区をモデルとして往診を併用したオンライン診療が始まったが定期的な診察、病状が一定の皆さんが対象であり、現在はさまざまに対応できるものではない。広域的に検討も含め少しずつ様子を見ながら拡大していきたい。
医師不在だった日義診療所の状況は
問 日義診療所は、昨年10月から約半年間、医師がいない状態が続いた。車がない患者等、木曽病院等に移った人は大変苦労した。町民から届いた声は。またこの間の体制はどうであったか。
答 他の病院への紹介状等で対応し、特に苦情はなかった。
看護師は正職員であるので本庁の事務職や三岳診療所の勤務に当たった。会計年度任用職員は、休診の間は雇用はなかったが4月以降は再開している。

長期間医師が不在だった日義診療所
答 他の病院への紹介状等で対応し、特に苦情はなかった。
看護師は正職員であるので本庁の事務職や三岳診療所の勤務に当たった。会計年度任用職員は、休診の間は雇用はなかったが4月以降は再開している。

観光商工課
スキー場の整備費は
問 スキー場の整備費はいくらか。
答 スキー場整備事業で支出しているのが3施設で1億円。新しい運営会社への支出は1億2千万円。
問 アスモグループの借入問題については、どう考えているのか。
答 アスモグループの問題については運営資金の問題もあり、町でしっかり対応していくべきだと考えている。
問 現状はどうなっているか。
答 アスモグループは清算の手続きを進めている。できるだけ早急にその手続きを進めるよう要望している。
問 マイアスキー場の施設整備費に2年間で2億4000万円支出するが、どう使われているのかの確認は行われているのか。
答 今現在、帳簿上の確認作業は終了している。現地確認はまだ済んでいない。
答 スキー場整備事業で支出しているのが3施設で1億円。新しい運営会社への支出は1億2千万円。
問 アスモグループの借入問題については、どう考えているのか。
答 アスモグループの問題については運営資金の問題もあり、町でしっかり対応していくべきだと考えている。
問 現状はどうなっているか。
答 アスモグループは清算の手続きを進めている。できるだけ早急にその手続きを進めるよう要望している。
問 マイアスキー場の施設整備費に2年間で2億4000万円支出するが、どう使われているのかの確認は行われているのか。
答 今現在、帳簿上の確認作業は終了している。現地確認はまだ済んでいない。
商品券の最終販売 問題なかったか
問 昨年のプレミアム商品券の販売については大いに評価できる。本年度の最終販売について購入できなかった住民が多くいたが、販売の仕方に問題はなかったか。
答 1次販売、2次販売をしたが、3300冊残ってしまった。早く販売しないと使用期間が短くなってしまうので、販売制限を無くして販売した。購入者が殺到してしまい、購入できなかった方が多くいた。販売の仕方に問題があったのでは、と反省している。
答 1次販売、2次販売をしたが、3300冊残ってしまった。早く販売しないと使用期間が短くなってしまうので、販売制限を無くして販売した。購入者が殺到してしまい、購入できなかった方が多くいた。販売の仕方に問題があったのでは、と反省している。
駒ケ岳避難小屋の概要は
問 駒ケ岳登山道の避難小屋整備事業の概要は。
答 2つの事業がある。8合目から7合目の避難小屋まで水を引く事業。7合目で発電しているが蓄電池が壊れたための交換事業。 登山客は令和3年度が550人、令和4年度が280人。(登山届を提出した人)

駒ケ岳の避難小屋・トイレ
答 2つの事業がある。8合目から7合目の避難小屋まで水を引く事業。7合目で発電しているが蓄電池が壊れたための交換事業。 登山客は令和3年度が550人、令和4年度が280人。(登山届を提出した人)

商品券の販売効果は
問 プレミアム商品券の販売効果は。
答 商品券で2億2500万円。飲食応援券で7500万円。
答 商品券で2億2500万円。飲食応援券で7500万円。
観光局の商品販売は進んでいるか
問 木曽おんたけ観光局の日本遺産を活かした商品販売は進行していないように見られるが。
答 マーケット調査やイベント参加でのPR、顧客のニーズ調査などを行っている。具体的な成果については知らされていない。
答 マーケット調査やイベント参加でのPR、顧客のニーズ調査などを行っている。具体的な成果については知らされていない。
稼ぐ力を身に着けることの重要性を
問 DМО(観光局)の重要な目的の一つは商品を作り、販売して自立するために稼ぐ力を身に着けること。(インバウンド事業では稼ぐ力が醸成できつつある)このことを町からも伝えて欲しいが。
答 DМОの設立目的である観光の面から地域の稼ぐ力を育てる会社であるということを念押しし、一緒に稼げる力をつけていけるよう努力する。
問 DМОは3年間交付金をいただきその後はどうなるのか。町の支援も含めて検討されているのか。
答 今後は稼ぐ力、収益にフォーカスしながら進めていかざるを得ないと考えている。
答 DМОの設立目的である観光の面から地域の稼ぐ力を育てる会社であるということを念押しし、一緒に稼げる力をつけていけるよう努力する。
問 DМОは3年間交付金をいただきその後はどうなるのか。町の支援も含めて検討されているのか。
答 今後は稼ぐ力、収益にフォーカスしながら進めていかざるを得ないと考えている。
建設農林課
今後も災害の事故繰越があるのでは
問 災害復旧費で事故繰越がある。5年度以降も事故繰越が出るのでは。
答 事故繰越は8事業残っている。それらは本年度中に処理しなければ補助金返納になるので年度内に竣工してもらうよう請負事業者にも話して進めている。
昨年の繰越明許費についても10箇所あるが、本年度中に復旧竣工してもらうよう進めている。本年度の災害復旧については、国の予算が付き次第進めていく。発注時期によって繰越となる場合もある。
答 事故繰越は8事業残っている。それらは本年度中に処理しなければ補助金返納になるので年度内に竣工してもらうよう請負事業者にも話して進めている。
昨年の繰越明許費についても10箇所あるが、本年度中に復旧竣工してもらうよう進めている。本年度の災害復旧については、国の予算が付き次第進めていく。発注時期によって繰越となる場合もある。
木質バイオマス拠点の将来は
問 チップを製造している木質バイオマス拠点施設の将来展望は。
答 木質チップの需要も増加しており、黒川の橋詰地区に木材ストックヤードや乾燥土場を整備し、これから増えてくる需要に対処していく。
答 木質チップの需要も増加しており、黒川の橋詰地区に木材ストックヤードや乾燥土場を整備し、これから増えてくる需要に対処していく。
農業新規就農者への支援は
問 農業新規就業者に対する支援はどうやっているのか。
答 新規就農者については5年間支援している。国からの補助も活用している。
問 昨年度新規就農者はいなかったのか。
答 イチゴの栽培をやっている方が1名いる。
問 その方にどんな支援をしているのか。
答 必要経費の一部を支援している。

日義地区のイチゴハウス
答 新規就農者については5年間支援している。国からの補助も活用している。
問 昨年度新規就農者はいなかったのか。
答 イチゴの栽培をやっている方が1名いる。
問 その方にどんな支援をしているのか。
答 必要経費の一部を支援している。

環境水道課
免許返納者に対して幅広く検討を
問 免許返納者に対して1万1000円の回数券を配布している。回数券をもらってもバスを利用しない方が結構いるのでタクシー利用等、幅広く検討ができないか。
答 免許返納数は令和4年度実績で46名、5年間のトータルで262名。チケットをもらっても利用が難しいという指摘もいただいている。ななまるタクシーもあり、公共システムの全体のバランスを考える必要があるので、公共交通協議会へも提案をしていきたい。
問 回数券を配った後の利用方法や利用回数の調査を行っているのか。何%くらいが利用し、使えない人がどのくらいいるのか等を把握できると、対策に生かせると思うが。
答 現時点で把握はしていないが、制度が適正に運用されているかどうか検証する必要もある。利用率を調べる何らかの方法を検討したい。
答 免許返納数は令和4年度実績で46名、5年間のトータルで262名。チケットをもらっても利用が難しいという指摘もいただいている。ななまるタクシーもあり、公共システムの全体のバランスを考える必要があるので、公共交通協議会へも提案をしていきたい。
問 回数券を配った後の利用方法や利用回数の調査を行っているのか。何%くらいが利用し、使えない人がどのくらいいるのか等を把握できると、対策に生かせると思うが。
答 現時点で把握はしていないが、制度が適正に運用されているかどうか検証する必要もある。利用率を調べる何らかの方法を検討したい。
交通システム これからの課題は
問 地域交通システムはコロナの影響も徐々に解消され利用は増えている。この状況を継続的なものとしていくための課題は。また、運転手の高齢化や確保の課題もあると思うが。
答 これは全国的な課題である。事業者からも要望書が出ている。人件費に苦労しており手当の要望などである。実際に所得を増やすことで運転手の確保につながるかの因果関係は分からず、採用担当者としては大変気になるところだと理解している。
問 令和5年度から乗務員の年間労働時間に上限が設けられる。これは人手不足につながらないか。
答 大変大きな課題。人件費は会社の経営に直結する話であり、どのように支援をしていくかは、会社側でどういう採用計画を作るかも含めての検討になる。双方で持ち寄って話をすることになると思う。
答 これは全国的な課題である。事業者からも要望書が出ている。人件費に苦労しており手当の要望などである。実際に所得を増やすことで運転手の確保につながるかの因果関係は分からず、採用担当者としては大変気になるところだと理解している。
問 令和5年度から乗務員の年間労働時間に上限が設けられる。これは人手不足につながらないか。
答 大変大きな課題。人件費は会社の経営に直結する話であり、どのように支援をしていくかは、会社側でどういう採用計画を作るかも含めての検討になる。双方で持ち寄って話をすることになると思う。
ICカード 試験実施の評価は
問 利便性の向上ということでICカード利用を試験的に実施した。どのように評価しているか。
答 実証期間は令和4年の12月1日から令和5年の2月28日の3カ月間。全体的にはスムーズに利用してもらったが、通常の都会の交通系ICカードとは異なり、その都度決済端末を運転手が操作しなければならないなどの戸惑いがあった。交付金を活用できるかもしれないが、本年度もDMO(観光局)で引き続き事業化をしたいという意向があるので実施したい。
答 実証期間は令和4年の12月1日から令和5年の2月28日の3カ月間。全体的にはスムーズに利用してもらったが、通常の都会の交通系ICカードとは異なり、その都度決済端末を運転手が操作しなければならないなどの戸惑いがあった。交付金を活用できるかもしれないが、本年度もDMO(観光局)で引き続き事業化をしたいという意向があるので実施したい。
簡易水道の有収水量・有収率は
問 簡易水道等特別会計で、水道の有収水量と有収率はどれくらいか。
答 簡易水道会計は、企業会計化はされていない。有収水量率の計算は現状で即答できる状況にはない。来年度以降は企業会計が導入されるので必然的に公表していく。
答 簡易水道会計は、企業会計化はされていない。有収水量率の計算は現状で即答できる状況にはない。来年度以降は企業会計が導入されるので必然的に公表していく。
水道管布設替えの状況は
問 水道事業で、管の布設替えは継続してやっていると思が、その状況は。
答 この2年ほど管の布設は行っていない。理由は幸沢川浄水場の改修で多額の費用を要しておりそちらを優先している。
問 浄水場の工事は長く続くと思うが、その見通しは。
答 浄水場の工事は令和7年度、その後も令和9年度までの工事もある。大規模改修を控えており、資産状況やキャッシュの状況を見ながら計画していく。
問 国の補助金のない事業であるから、財政が回っていかないのではないか。補助金は要求できないのか。
答 国や県に対しての要望は、県の町村会にまとめて要請している。今年度の要望が固まり、11月以降に県や国へ上げていく段階。場合によっては今年度の要望に付け加えるようにしていく。
答 この2年ほど管の布設は行っていない。理由は幸沢川浄水場の改修で多額の費用を要しておりそちらを優先している。
問 浄水場の工事は長く続くと思うが、その見通しは。
答 浄水場の工事は令和7年度、その後も令和9年度までの工事もある。大規模改修を控えており、資産状況やキャッシュの状況を見ながら計画していく。
問 国の補助金のない事業であるから、財政が回っていかないのではないか。補助金は要求できないのか。
答 国や県に対しての要望は、県の町村会にまとめて要請している。今年度の要望が固まり、11月以降に県や国へ上げていく段階。場合によっては今年度の要望に付け加えるようにしていく。
生涯学習課
体育施設利用者 少ないのでは
問 開田高原体育館利用者数643人、総合グラウンド利用者数340人とあるが利用者が少ないのではないか。
答 体育施設の利用状況は地域で差がある。利用者数や施設の整備維持管理については、地域の方ともご相談しながら今後考えていかなければならない課題である。
問 開田高原体育館の修繕工事に200万円強の経費に対し、643人の利用はどうかと思うが。
答 利用度と修繕費用とは天秤にかけながら検討する必要があり、地域の方の意見も聞きながら進めていく課題と思っている。

利用者が減っている開田高原体育館
答 体育施設の利用状況は地域で差がある。利用者数や施設の整備維持管理については、地域の方ともご相談しながら今後考えていかなければならない課題である。
問 開田高原体育館の修繕工事に200万円強の経費に対し、643人の利用はどうかと思うが。
答 利用度と修繕費用とは天秤にかけながら検討する必要があり、地域の方の意見も聞きながら進めていく課題と思っている。

障害者用昇降機 残しておいては
問 旧上田小学校の階段についている障害者用の昇降機について、今必要かどうかは別として、もし使えるものであれば残しておいてはどうか。
答 確認したところ現在、昇降機は撤去されている。
答 確認したところ現在、昇降機は撤去されている。
文化交流センター 減免措置の考え方は
問 文化交流センターの運営で、光熱水費等が高騰しており本年7月の利用からエアコン使用料が請求されるようになっている。また文化交流センターのボイラーにかかる燃料費は効率的な暖房方法ではないと思う。減免措置など冷暖房に対する町の考え方は。
答 町の公共施設は内規によって減免団体を指定しており、使用料もそれに該当すれば減免をしている。冷暖房費はあまり減免にしているケースはないが、コールセンターの運営委員会で検討していきたい。
答 町の公共施設は内規によって減免団体を指定しており、使用料もそれに該当すれば減免をしている。冷暖房費はあまり減免にしているケースはないが、コールセンターの運営委員会で検討していきたい。
日義支所
高速バス利用者の駐車 影響あるのでは
問 日義の道の駅で、土日になると高速バスに乗るため駐車場に車を停めて高速バスで東京方面などへ出かける方がいる。道の駅の運営に対して影響があると思うが、高速バスの事業者も交えた協議が必要ではないか。
答 事業者の話では、バス停は許可を得ているが駐車場は特に借りてはいない。道の駅の会議もあるので、その中で話をする。
答 事業者の話では、バス停は許可を得ているが駐車場は特に借りてはいない。道の駅の会議もあるので、その中で話をする。
開田支所
直営のやまゆり荘 利用者は
問 開田高原の日帰り温泉やまゆり荘は、直営になってから利用客はどうなっているのか。
答 令和4年度の入り込み者数は3万1531人。前年度からは2588人の増加で8.9%の増。コロナ前の数字にはまだ及ばないが令和4年の実績から見ると、徐々に回復してきた。食堂は今年度8月再開しており、近くに食事ができる場所が少ないので本当に助かるといった声がある。また運営は健康ラボ自体が本業に専念する必要があるので、やまゆり荘の経営までも手が回らない状態である。しばらくこの状態を続けていきたい。

食堂を再開したやまゆり荘
答 令和4年度の入り込み者数は3万1531人。前年度からは2588人の増加で8.9%の増。コロナ前の数字にはまだ及ばないが令和4年の実績から見ると、徐々に回復してきた。食堂は今年度8月再開しており、近くに食事ができる場所が少ないので本当に助かるといった声がある。また運営は健康ラボ自体が本業に専念する必要があるので、やまゆり荘の経営までも手が回らない状態である。しばらくこの状態を続けていきたい。

健康ラボの自立をどう考えているか
問 おんたけ健康ラボは国の交付金をいただいて運営している。自立に向けてどのように考えているか。
答 令和4年度からは、町単独で800万円の補助をしている。企業健保組合へもPRしている。令和4年度は、林野庁などが推進する森林サービス産業モデル地域の選定を受けて、エビデンス取得モニターツアーを実施した。そのほかワーケーションや化粧品企業との連携などさまざまな事業展開をしている。健保組合へのPRを積極的に行って、自立へ向けて取り組んでいきたい。
答 令和4年度からは、町単独で800万円の補助をしている。企業健保組合へもPRしている。令和4年度は、林野庁などが推進する森林サービス産業モデル地域の選定を受けて、エビデンス取得モニターツアーを実施した。そのほかワーケーションや化粧品企業との連携などさまざまな事業展開をしている。健保組合へのPRを積極的に行って、自立へ向けて取り組んでいきたい。
三岳支所
ビジターセンター 収入の方法考えては
問 御嶽山ビジターセンターの施設管理委託料として743万円が支払われている。少しでも収入の方法を考えた方が良いのでは。
答 基本的にビジターセンターは、御嶽山の火山防災情報や魅力を発信する施設であり、今後も入館料無料で運営することを基本にしている。美術館のように入場料での収益をという話もあるが、自立できるようになればとは思っている。指定管理料を少なくする努力は必要である。

噴火の痕跡が残る双眼鏡やメガネなども展示しているビジターセンター
答 基本的にビジターセンターは、御嶽山の火山防災情報や魅力を発信する施設であり、今後も入館料無料で運営することを基本にしている。美術館のように入場料での収益をという話もあるが、自立できるようになればとは思っている。指定管理料を少なくする努力は必要である。

陳情
〇「健康保険証」の存続に関する意見書の提出を求める陳情書
内容
現行の健康保険証を廃止し、マイナンバーカードに一本化する法案が成立したが、マイナ保険証に関するトラブルが続出し多くの患者や国民が不安を抱えている。安心して医療を受けられるように保険証の存続を求めるもの。
提出者
長野県保険医協会
会長 宮沢裕夫
松本地区社会保障推進協議会
会長 久保田真
付託委員会
社会文教常任委員会
審査結果
継続審査
討論
審査結果に対し中村博道議員から反対討論、松井淳一議員から賛成討論があり採決の結果、賛成多数で継続審査になった。
反対議員
上田・下島・中村(博道)
賛成議員
松井・原田・橘・藤田・中村(博保)・大目・栩本
現行の健康保険証を廃止し、マイナンバーカードに一本化する法案が成立したが、マイナ保険証に関するトラブルが続出し多くの患者や国民が不安を抱えている。安心して医療を受けられるように保険証の存続を求めるもの。
提出者
長野県保険医協会
会長 宮沢裕夫
松本地区社会保障推進協議会
会長 久保田真
付託委員会
社会文教常任委員会
審査結果
継続審査
討論
審査結果に対し中村博道議員から反対討論、松井淳一議員から賛成討論があり採決の結果、賛成多数で継続審査になった。
反対議員
上田・下島・中村(博道)
賛成議員
松井・原田・橘・藤田・中村(博保)・大目・栩本